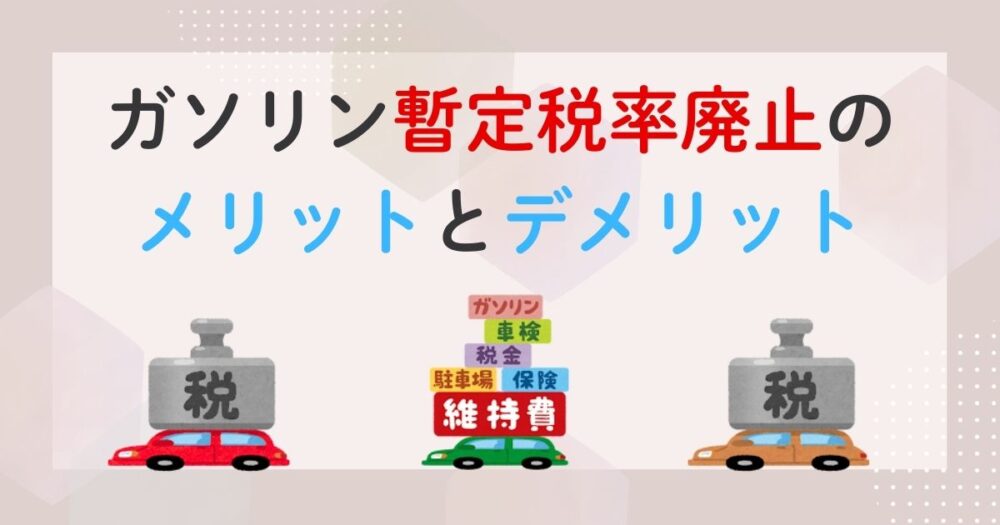ガソリンの価格を押し上げている要因の一つに「暫定税率」があります。
本来は一時的な措置でしたが、1974年に導入されてから半世紀近くたった今も続いている制度です。
政府や国会で廃止に向けた議論が進む一方で、財源や環境政策との兼ね合いから賛否が分かれています。
本記事では「ガソリン暫定税率廃止」のメリットとデメリットを整理し、生活や社会にどのような影響が及ぶのかを分かりやすく解説します。
「もし廃止されたら、あなたのガソリン代や日常生活はどう変わるのか?」
その答えを探っていきましょう。


ガソリン暫定税率とは?
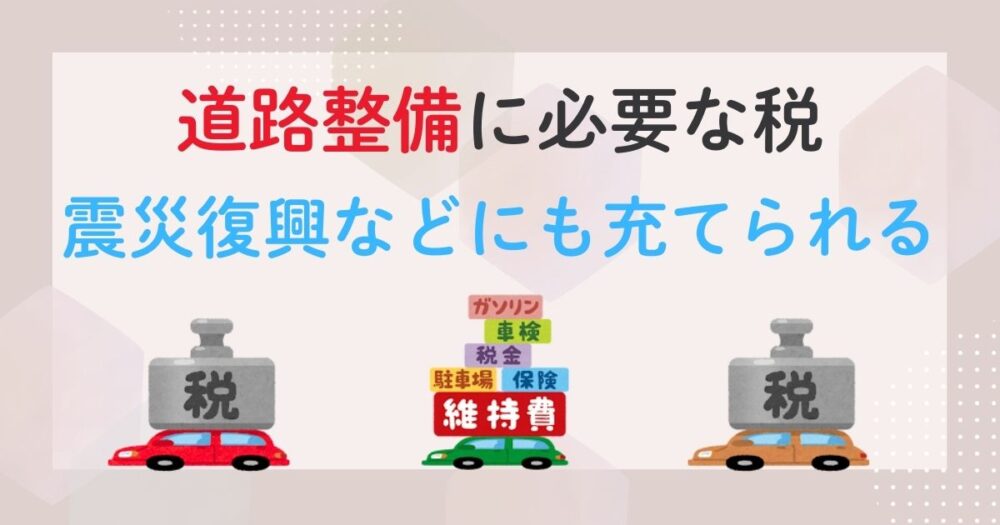
暫定税率が導入された経緯
ガソリン暫定税率は、1974年に道路整備の財源を確保する目的で導入されました。
本来は「時限的措置」として設定され、一定期間で終了するはずでしたが、その後も延長が繰り返され今日まで続いています。
現在のガソリン税は1リットルあたり53.8円で、そのうち25.1円が暫定税率による上乗せ部分です。
では、なぜ時限的なはずの制度が現在まで続いているのでしょうか?
次にその理由を見ていきましょう。
暫定税率が現在も続く理由
2009年度に道路特定財源は廃止され、税収は一般財源に組み込まれました。
それでも暫定税率による収入は国と地方を合わせて年間約2.23兆円(2024年度見込み)にのぼり、国の財政運営を支える柱となっています。
特に震災復興や社会保障費など幅広い分野に充てられるようになり、単なる「道路整備目的の税」ではなくなったことが存続の大きな理由です。
こうした背景から、歴代政権も容易には廃止に踏み切れませんでした。
暫定税率廃止のメリット
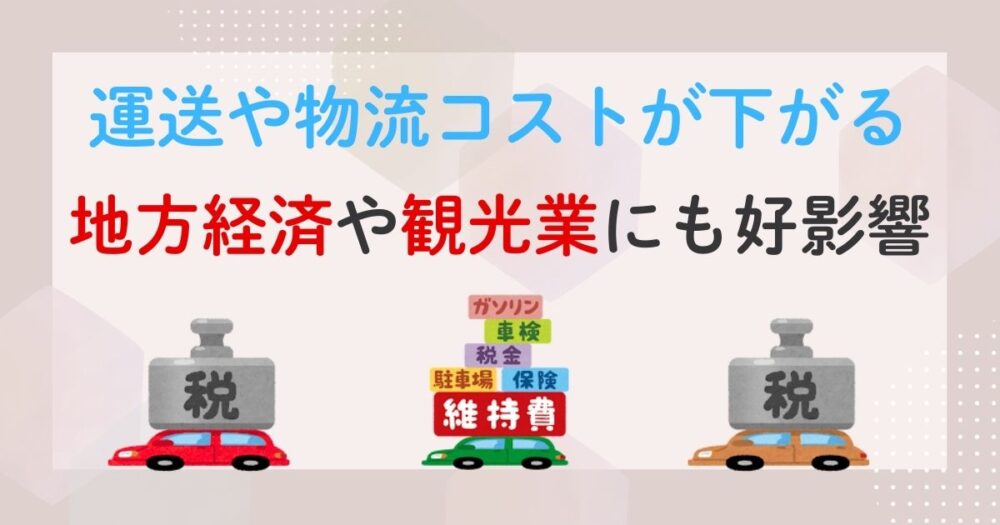
家計への直接的な負担軽減
ガソリン暫定税率が廃止されれば、1リットルあたりおよそ25円の負担が軽くなる可能性があります。
仮に1か月で50リットル給油する家庭なら、月1,250円、年間で1万5,000円ほどの節約につながる計算です。
ガソリン価格は家計への影響が大きく、特に地方の車依存度が高い世帯では、その恩恵をより強く感じられるでしょう。
日常的な移動や買い物のコスト削減は、生活全体の安心感にも直結します。
物価全体の抑制効果
ガソリン価格は物流コストに直結するため、暫定税率が廃止されれば幅広い物価抑制効果も期待できます。
燃料費が下がれば、運送業や小売業の負担も軽減され、食品や日用品など生活必需品の価格安定につながります。
特に、燃料高騰が続いた近年では「物価上昇=生活不安」の要因となっており、暫定税率廃止は物価対策の一環としても注目されています。
家計全体の圧迫を和らげる点で、大きな利点といえるでしょう。
地方経済や観光への波及効果
ガソリン代が下がると、自家用車での移動がしやすくなり、地方経済や観光業にも好影響を与える可能性があります。
車で訪れる観光地やレジャースポットの需要が高まり、宿泊や飲食など地域産業の活性化につながります。
また、ガソリン代の高騰によって外出を控えていた層が動き出せば、地域内の消費循環も回復しやすくなります。
特に公共交通が限られる地方では、暫定税率廃止の恩恵が経済全体に広がると期待されています。
暫定税率廃止のデメリット
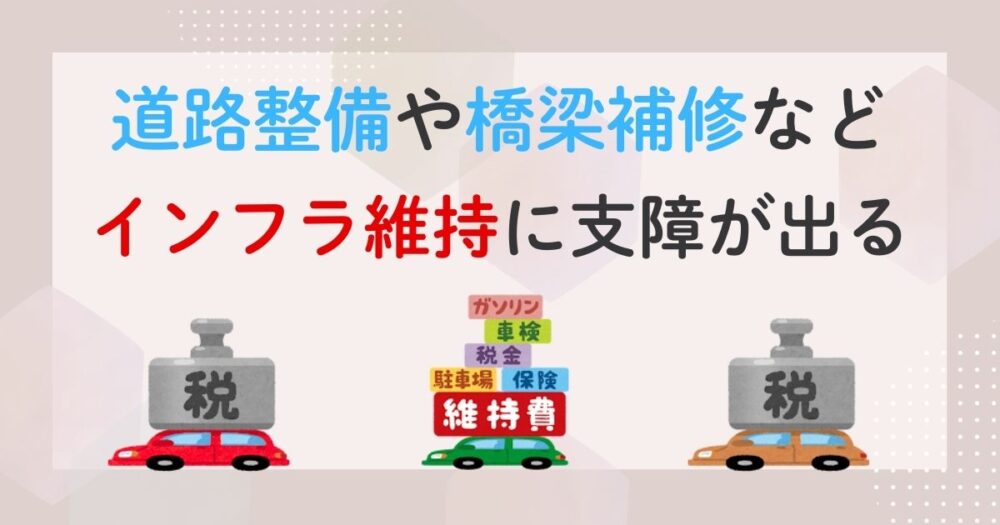
道路整備への影響
ガソリン暫定税率による税収は、国と地方を合わせて年間約2.23兆円規模(2024年度見込み)に上ります。
もし廃止されれば、この財源が失われることで道路整備や橋梁補修といったインフラ維持に支障が出る可能性があります。
老朽化が進む日本の道路網にとって、安定した財源の確保は不可欠です。
代替の財源が見つからないまま廃止を実行すると、安全性や利便性に影響する懸念が拭えません。
ガソリン代は思ったほど安くならない?
現在、ガソリン価格を抑えるために1リットルあたり10円程度の補助金が導入されています。
暫定税率廃止と同時にこの補助金が終了する場合、実際の値下げ幅は25円ではなく15円前後にとどまる可能性があります。
つまり、期待していたほどの恩恵を受けられないケースも想定されます。
消費者の「思ったほど安くならない」という失望感は、政策への不信感にもつながりかねません。
ガソリン代が下がるとEV普及は遠のく?
ガソリン価格が下がれば消費が促進され、自動車利用が増加する可能性があります。
これは二酸化炭素の排出増につながり、政府が掲げる脱炭素目標やEV普及政策に逆行する結果となりかねません。
近年はカーボンプライシングや環境税など「利用を減らす方向」の政策が重視されており、暫定税率廃止はその流れに逆行する点で批判も強いです。
環境対策と家計支援のバランスが難しい課題となります。
流通や販売現場の混乱
暫定税率が廃止されると、価格改定のタイミングで流通や販売現場に混乱が生じる可能性があります。
特に、卸業者やガソリンスタンドでは、在庫を抱えた状態で価格が大幅に下がれば損失につながります。
そのため、廃止直前に「買い控え」が起こり、供給や資金繰りに支障が出るケースも想定されます。
円滑に移行するには、事業者への補償や調整策が欠かせません。
今後の見通しと注目点
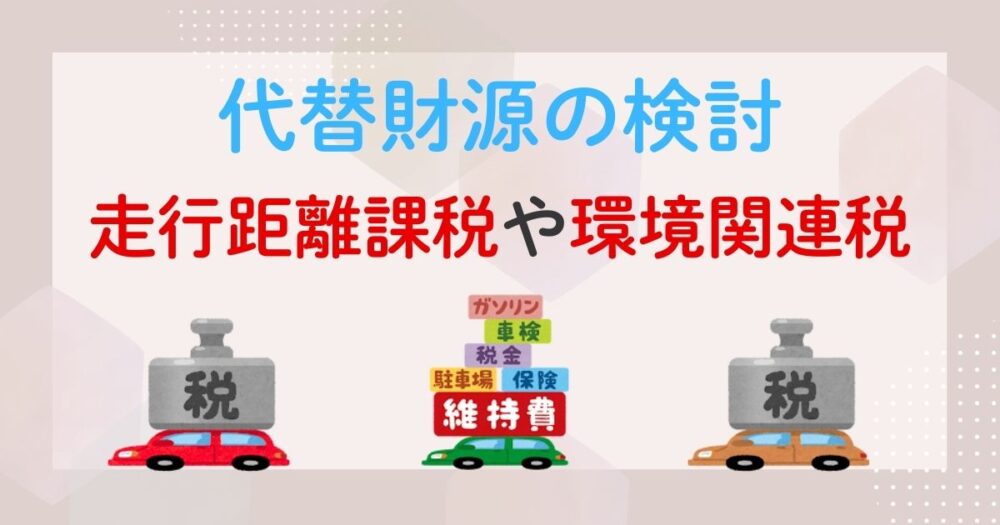
政治的な動向
ガソリン暫定税率の廃止は、これまでも与野党の間で繰り返し議論されてきました。
2025年には野党が法案を提出し衆議院で可決されましたが、参議院で成立には至っていません。
一方で与党内でも生活支援の観点から廃止論が高まっており、11月の実施を目指す協議が進められています。
政治的な駆け引きが続く中で、最終的にどのような形で落ち着くのかが最大の注目点となっています。
代替財源の検討
暫定税率が廃止された場合の最大の課題は、失われる税収の穴をどう埋めるかです。
候補として挙げられているのが「走行距離課税」や「環境関連税」など、自動車利用全般に広く課税する仕組みです。

しかし、地方居住者の負担増や公平性への懸念から反発も大きく、実現には時間を要すると見られます。
単に廃止するだけではなく、どのような新しい制度とセットで導入されるかが重要になります。
まとめ:ガソリン暫定税率廃止の真の影響をどう見るか
ガソリン暫定税率の廃止は、家計や物流コストの軽減といったメリットをもたらす一方で、国や地方の財源不足、環境政策への逆行、流通現場の混乱など多くの課題も抱えています。
特に「ガソリン代が本当に下がるのか」「失われる税収をどう補うのか」という点は、生活に直結する大きな問題です。
廃止が実現すれば一時的に負担は軽減されますが、代替財源のあり方や今後の政策によっては、新たな負担が生じる可能性も否定できません。
消費者としては、目先の値下げだけでなく、長期的にどのような影響があるのかを冷静に見極めていく姿勢が求められます。