ちょっとしたトラブルや不安があると、すぐに警察へ通報してしまう…そんな人は少なくありません。
『またかと思われているのでは?』
『本当に必要なときに対応してもらえなくなるのでは?』
と不安に感じる人もいるでしょう。
実際に通報をしすぎることは、社会的にもリスクがあり、誤った方法は逆効果になる場合もあります。
本記事では通報しすぎのリスクと、正しい通報・相談の使い分けを分かりやすく解説します。
警察への通報をしすぎるとどうなる?
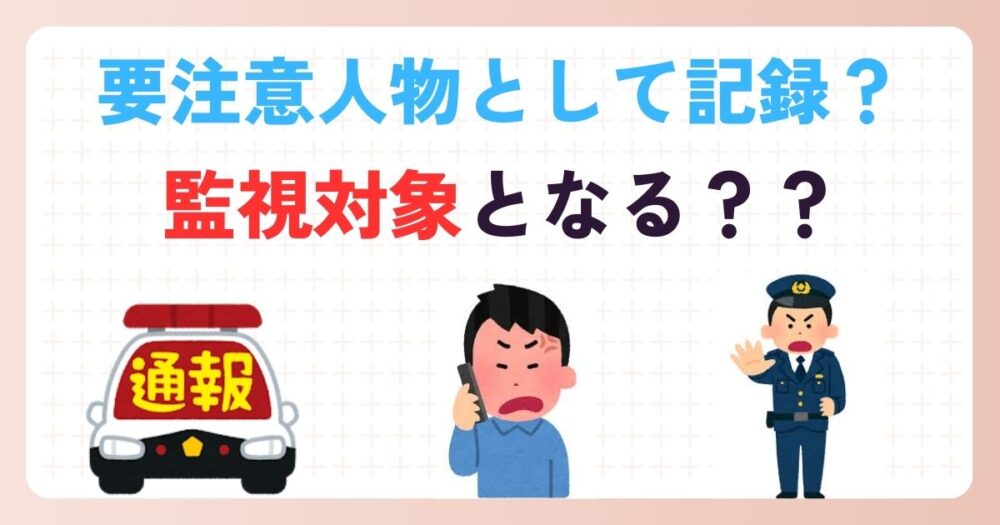
通報履歴が残り「要注意人物」と扱われる可能性
警察は110番通報の内容を記録として残します。
頻繁に通報していると「この人は過敏に反応する傾向がある」と認識され、必要以上の通報を繰り返す人物として扱われることもあります。
もちろん違法ではありませんが、いざというときに「またこの人か」と受け止められてしまう恐れがあるのが問題です。
警察の内部では要注意人物として記録され、監視対象のように扱われてしまうリスクもあります。
些細な通報を繰り返すと本当に危険なときに迅速な対応を受けられなくなる恐れがある
本来110番は人命や重大事件に対応するための窓口です。
「車の窓からタバコを捨てた」
「ウインカーを出さずに曲がった」
など、小さな違反や不快な行動まで毎回通報してしまうと、本当に危険な場面で通報してもまた些細なことかもしれないと疑われ、必要な支援を受けられない危険性もあります。
使いすぎは自分の安全を逆に脅かすリスクがあるのです。
虚偽や悪質な通報は処罰対象になる
「事件が起きている」と虚偽の内容を通報すると、軽くても軽犯罪法、重ければ威力業務妨害罪に問われる可能性があります。
繰り返し虚偽通報をすれば、警察の業務を妨害したと判断され、逮捕や罰金に発展することもあります。
意図的ではなくても、事実と異なる情報を何度も申告していると、結果的に「虚偽通報」と見なされかねません。
こうした話を大きくし過ぎた通報は、冗談では済まされないリスクを伴います。
なぜ通報しすぎてしまうのか?心理的な背景

不安や不満を解消する手段としての通報
通報癖の背景には、日常のストレスや不満も影響しています。
周囲の小さな違反や気に入らない行動に過敏に反応し、「警察に伝えることで気が済む」といった心理につながるのです。
その結果、通報そのものが不安や苛立ちを解消する手段となり、行動が習慣化してしまいます。
気づかないうちに通報すること自体が安心や満足感につながり、生活の一部のようになってしまうのです。
小さな不満を流せない性格が通報につながる
騒音や駐車の迷惑行為、ちょっとしたマナー違反などに対して、「許せない」「見過ごせない」と感じやすい人がいます。
小さなルール違反や不快な行動に強く反応してしまう性格は、結果的に通報へと直結しやすいのです。
日常の小さな苛立ちを警察にぶつけてしまうことで、通報が習慣のように繰り返されていきます。
通報そのものが安心材料になるケース
繰り返し通報していると、「通報したからもう大丈夫」という安心感が生まれます。
警察が駆けつけてくれるかどうかに関係なく、電話をかけた時点で不安が解消されるのです。
こうなると通報は本来の「安全確保手段」ではなく「精神安定のための行動」に変質します。
このタイプは本人も「やりすぎかな?」と不安を抱えながら止められず、結果として通報回数が増えてしまいます。
通報を減らすための代替手段と正しい使い分け
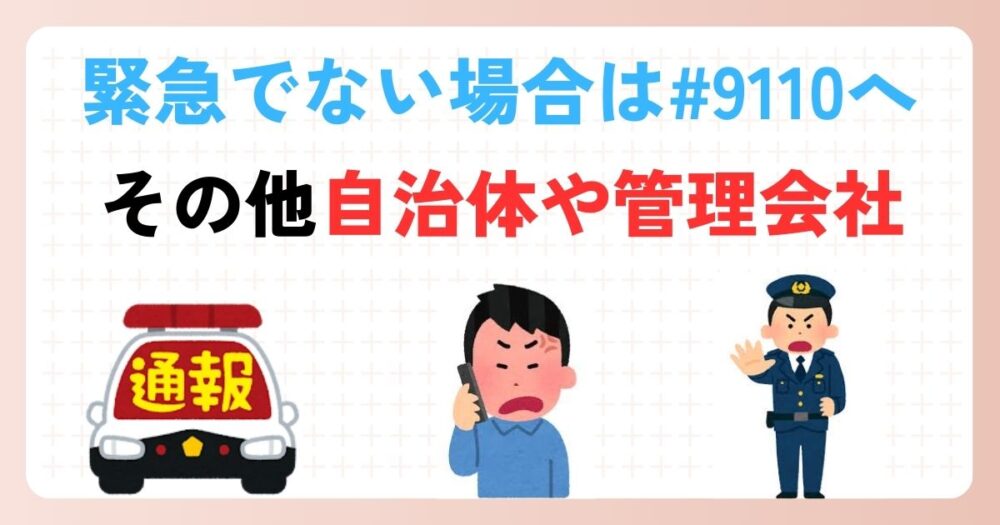
110番と#9110(警察相談ダイヤル)の違い
110番は人命に関わる事件や事故のための「緊急専用回線」です。
一方、#9110は「すぐに危険はないが不安や相談をしたいとき」に使える全国共通の警察相談ダイヤルです。
騒音や嫌がらせ、トラブルの相談は#9110が適切で、110番を乱用せずに済みます。
実際に警察庁も#9110の利用を呼びかけており、「緊急」と「相談」の使い分けがトラブル防止の第一歩になります。
9110や自治体など、状況に応じた相談先
緊急性の低い問題は、110番ではなく次の窓口を利用するのが適切です。
これらの窓口を把握しておくことで、状況に応じて適切な対応先を選べるようになります。
その結果、問題解決までの流れがスムーズになり、警察の緊急窓口に不必要な負担をかけずに済むのです。
通報前に「記録」を残して冷静に判断する
気になった出来事があったとき、すぐに110番に電話するのではなく「日時・状況・相手の行動」をメモや写真で記録しておくのも有効です。
証拠が残れば後から冷静に見返すことができ、「これは警察に通報すべきか、それとも相談で済むか」と判断がつきやすくなります。
結果的に無駄な通報が減り、必要なときに的確な行動を取れるようになります。
正しい通報のあり方とは?

本当に危険なときはためらわず通報する
110番は「命の危険が迫っている」「犯罪が進行している」場面では迷わず使うべきものです。
遠慮しすぎて通報が遅れると、事件・事故の被害が拡大する可能性があります。
たとえば不審者が侵入しようとしている、暴力を受けている、火災や交通事故が発生したなど、緊急性が高い場合には速やかに通報してください。
こうした本来の目的で使うことが、通報を社会的に正しい行動として保つポイントです。
「警察に頼る」と「自分で解決する」のバランスを考える
通報を繰り返してしまう人は「身近な細かな出来事をすぐ警察に頼ってしまう」傾向が強いですが、すべてを外部に頼ることは社会的な信頼を損なう場合もあります。
小さなトラブルは管理会社や地域のルール、自分の対処法でカバーし、大きな事件・事故だけを警察に任せる。
そうしたバランスを意識することで、警察に適切に協力を求められるようになり、本当に必要なときに迅速な対応を得られる可能性も高まります。
まとめ:110番は“緊急専用”、相談は他の窓口へ
警察への通報は、命や財産を守るために欠かせない仕組みです。
しかし、ちょっとした不安や小さなトラブルまで毎回110番にかけてしまうと、警察の信頼を失うだけでなく、本当に必要なときに動いてもらえないリスクも高まります。
さらに、虚偽や悪質な通報は処罰の対象にもなり得ます。
「また通報してしまった」と感じている人は、#9110や自治体の相談窓口など、110番以外の選択肢を知ることが大切です。
記録を残して冷静に判断し、緊急時は迷わず110番へ、相談ごとは適切な窓口へ。
この使い分けが、自分と社会を守る最も賢い方法です。
