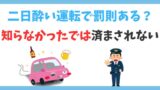飲酒運転の車に同乗していただけで、責任を問われる可能性があることをご存じでしょうか。
しかも、免許を持っていない人でも処罰の対象になり得るため、状況を軽く考えるのは危険です。
実際には「飲酒していたことを知っていたかどうか」や「同乗の経緯」によって、罪の有無が判断されますが、「知らなかった」という言い訳は基本的には通用しません。
この記事では、飲酒運転の同乗者に課せられる法的責任や、免許の有無による違い、処罰の具体例まで詳しく解説します。
正しい知識を持ち、自分を守る判断力を養いましょう。
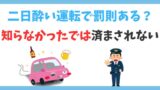
飲酒運転同乗罪と免許の有無による責任の違い

同乗者も処罰対象になる成立条件
飲酒運転は運転者だけの問題ではありません。
道路交通法第65条第4項では、酒気帯びの運転者と知りながら同乗した者にも罰則が科される「飲酒運転同乗罪」が規定されています。
この罪が成立するには、「運転者が飲酒していると認識していたこと」と「自らの意思で同乗したこと」の2点が重要な要件となります。
たとえ免許を持たない同乗者であっても、これらの要件に当てはまれば処罰の対象となるため、状況を軽視せず冷静な判断が必要です。
免許の有無で変わる責任範囲
運転免許を持っていない同乗者であっても、飲酒運転を知りながら乗車していた場合には、刑事責任を問われることがあります。
ただし、免許を持っていない人には行政処分(免許停止・取消)は適用されません。
しかし、同乗行為が「重大違反を唆した」と判断されると、将来あらためて免許を取得しようとした際に、公安委員会の判断で交付が拒否や保留される可能性があります。
このような判断は全国の公安委員会で制度として運用されており、免許をまだ持っていない人にも適用される仕組みです。
刑事・行政・民事で問われる責任

飲酒運転同乗罪による刑事罰の重さ
飲酒運転の車に同乗し、運転者の飲酒を知っていた場合は、「飲酒運転同乗罪」として刑事責任が問われます。
処罰は想像以上に重く、以下のように区分されています。
- 酒気帯び運転の同乗
2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金 - 酒酔い運転の同乗
3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
この罪は、「自らの行動によって危険な運転を容認した」とみなされることに基づいています。
また、警察の取り調べでは「本当に飲酒を知っていたか」が詳細に調べられ、アルコールのにおいや周囲の状況などから「気づけたはず」と判断されれば、言い逃れが通用しないケースも少なくありません。
免許保持者が同乗した場合に科される行政処分
免許を所持している同乗者の場合、刑事罰に加えて行政処分が下されることもあります。
飲酒運転同乗罪においては、運転者と同等の違反点数が加算されるのが原則です。
- 呼気1Lあたり0.15mg以上0.25mg未満:13点(免許停止90日相当)
- 呼気1Lあたり0.25mg以上:25点(免許取消・欠格期間2年相当)
- 酒酔い運転:35点(免許取消・欠格期間3年相当)
このため、違反歴がなくても一度の同乗で免停や取消処分に直結する可能性があります。
また、過去の違反歴と累積されれば処分はさらに重くなり、再犯や他の違反が重なれば、同乗罪だけでも免許取消に至るケースもあります。
事故時の民事責任(損害賠償)
飲酒運転の車に同乗していた状態で事故が発生した場合、同乗者も民事責任を問われる可能性があります。
たとえば、運転者が加害者となり、損害賠償が発生した際に「飲酒運転を容認していた」と判断されれば、共犯的立場として賠償責任を分担させられることもあります。
また、同乗者自身が負傷したとしても、被害者とはみなされず、補償が受けられないケースもあります。
「飲酒運転だと知りながら乗っていた」という事実が、自己責任とみなされるリスクは無視できません。
同乗者が処罰されないケース

「飲酒を知らなかった」場合
同乗者が処罰されるかどうかを左右する最大のポイントは、「運転者が飲酒していたことを知っていたかどうか」です。
飲酒の事実を知らずに乗っていた場合、同乗罪は基本的に成立しません。
たとえば、運転者が飲酒を隠していたり、アルコールのにおいや挙動にも明らかな異変が見られなかった場合など、認識のなかった事情があれば処罰されない場合もあります。
ただし、明らかに酒のにおいがしていた、飲み会帰りだったなどの状況があれば、「気づけたはず」として有罪となることもあるため慎重な対応が求められます。
「意思に反して乗った」場合
もう一つの免責条件は、「同乗する意思がなかった場合」です。
たとえば、「強引に車に乗せられた」「断ったのにしつこく迫られて仕方なく乗った」といったケースでは、同乗の意思がなかったと判断される可能性があります。
拒否しても強引に発進されたような場合には、自分で同乗を選んだとは言えないため、処罰の対象外とされることがあります。
ただし、断る余地があったのに黙認したと見なされれば、責任を問われる可能性もあるため注意が必要です。
同乗者として取るべき予防策

飲酒の可能性を感じたら断る
運転者が酒を飲んでいるかもしれないと感じた場合は、たとえ確証がなくても乗車を断る勇気が必要です。
「もしかして?」と思った時点で疑うべきであり、強引に乗せようとされても毅然とした態度を取ることが大切です。
あとで「知らなかった」と主張しても、周囲の状況やにおいなどから“気づけたはず”と判断されれば、責任を問われる可能性があります。
リスクのある状況には、そもそも近づかない選択が安全です。
代替手段を用意しておく
飲み会や外出の場では、あらかじめ代行運転・タクシー・公共交通機関などの選択肢を考えておくことも重要です。
事前に移動手段を確保していれば、飲酒運転の車に頼る必要がなくなります。
また、運転者が飲む可能性があることが分かっているなら、代行サービスの連絡先やアプリを用意しておくのも有効な手段です。
「その場しのぎ」の判断ではなく、計画的な行動がトラブルを未然に防ぎます。
同乗前に必ず運転の可否を確認する
車に乗る前には、必ず運転者の状態を確認しましょう。
飲み会帰りや宴席の後であれば、表情や話し方、歩き方に変化がないかを観察することも大切です。
「大丈夫?」と一言声をかけるだけでも、トラブルを回避できる可能性があります。
何も確認せずに乗るという行為は、裁判で「飲酒の可能性を軽視した」と受け取られかねません。
同乗する責任は、運転者だけでなく、乗る側にもあるという意識を忘れずに行動しましょう。
まとめ:飲酒運転 同乗者・免許なしのリスク
飲酒運転の車に同乗することは、たとえ免許がなくても重大な法的リスクを伴います。
運転者の飲酒を認識していた場合には、同乗罪として刑事罰が科される可能性があるため注意が必要です。
また、事故時には民事責任を問われることもあり、自分自身が被害者になれないケースもあります。
リスクを回避するためには、事前の確認と適切な判断が何より重要です。
「知らなかった」では済まされない時代だからこそ、正しい知識と行動が自分を守る力になります。