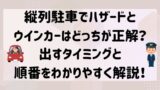クルマに乗っていると、さまざまな場面で見かけるハザードランプ。
「後続車に渋滞を知らせる」
「ありがとうの合図」
「駐車のサイン」
など、本来は緊急時に使う装置でありながら、日本では慣習的に幅広い意味を持つようになりました。
便利な合図として親しまれている一方で、法的に定められた使い方ではないため、誤解を招いたりトラブルの原因になることもあります。
だからこそ、どんな場面でどう使われているのかを知っておくことが重要です。
この記事では日常的によく見られるシチュエーション別に、その意味や注意点、海外との違いまで整理して解説します。
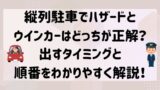
まずは基本をおさらい!ハザードランプってどんな意味?

ハザードランプ(正式には非常点滅表示灯)は、車両に異常がある時や周囲に注意を促したい時に使う合図です。
両側のウインカーが同時に点滅することで、「この車は通常と違う状態にある」と後続や周囲に伝える役割を果たします。
故障や緊急停止時の使用は法律で定められていますが、それ以外の場面では“慣習”として使われている例も多くあります。
意味や使い方を誤解するとトラブルの原因にもなるため、正しい知識を持つことが安全運転につながります。
【使用例①】後続車に渋滞を知らせる

高速道路で渋滞の末尾に近づいたときは、後続車への追突防止のためにハザードランプを点灯します。
出典:中日本高速道路株式会社
渋滞後方ではハザードランプを点灯(6ページ目参照)
https://www.cnexco.co.jp/images/news/6067/16011f3495fbaeb6a1a65cb18324febd.pdfutm_source=chatgpt.com
これは法律で明記されてはいませんが、多くのドライバーが実践しており、高速道路会社や警察も注意喚起として推奨している行動です。
使い方のコツは、ブレーキと同時にハザードを点けて後続車が減速したのを確認したら消すこと。
長く点けっぱなしにするのではなく、必要な場面だけ短く活用するのがスマートです。
安全を守るための合図として、もっとも実用的な使い方の一つといえます。
【使用例②】譲ってもらった時の「ありがとう」
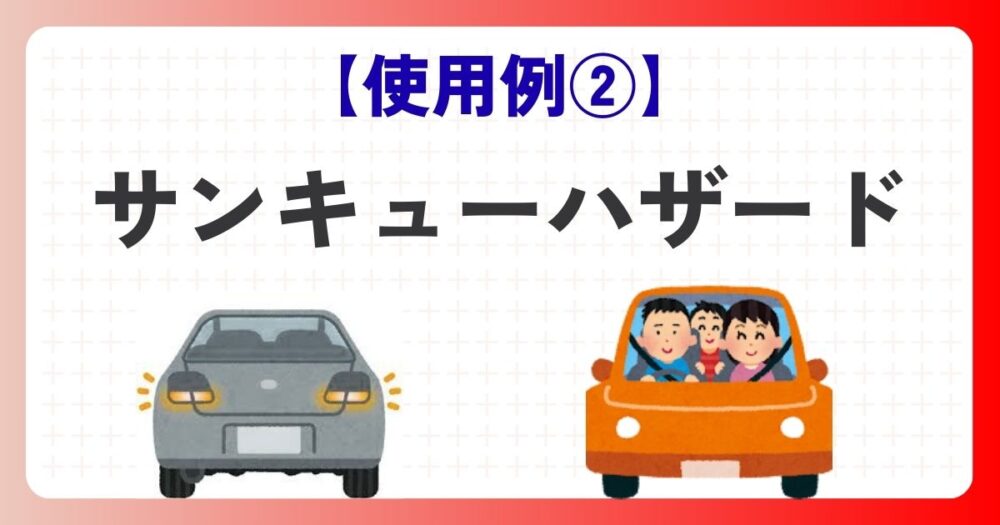
車線変更や合流時などで道を譲ってもらった際、ハザードを数回点滅させて感謝を伝える「サンキューハザード」。
法律上の決まりはなく、正式な用途ではありませんが、日本ではマナーの一つとして広く使われています。
ただし、使い方を間違えると逆効果になることも。
たとえば車間が詰まっている場面や夜間などは、まぶしさや誤解を与える可能性があります。
使うなら2~3回程度にとどめ、安全を確認してからにしましょう。
「ありがとう」の気持ちは大切ですが、無理に使う必要はなく、状況を見て判断するのが理想的です。

【使用例③】強引な割込みの「すまん、ありがと」

車線に強引に割り込んだ直後、ハザードを2~3回点ける車を見かけることがあります。
これは「すまん、でもありがと」といった、自己完結型の謝罪と感謝を一度に込めたつもりの合図でしょう。
しかし本来、ハザードは危険を知らせるための灯火であり、反省やお礼のサインではありません。
割込みが乱暴だった場合、かえって相手をイラつかせたり、トラブルの原因になることも。
実際にあおり運転の引き金になったケースも存在します。
ハザードで丸く収めるのではなく、まずは安全な車間距離と余裕ある運転を心がけることが、誤解や衝突を防ぐ基本です。
【使用例④】故障や緊急停止

故障や事故などで車を路肩や道路上に止めるときは、まずハザードランプを点けて後続に知らせるのが基本です。
その後は、高速道路や自動車専用道では乗員をすぐにガードレールの外側へ避難させ、車両後方に停止表示器材(三角表示板※22ページを参照)を設置することが義務づけられています。
これは努力義務ではなく、道路交通法で定められた明確な義務です。
ハザードはあくまで「最初の注意喚起」であり、その後の安全確保や通報が極めて重要。
車内にとどまるのは非常に危険なので避けましょう。
万一に備え、手順を事前に把握しておくと安心です。
【使用例⑤】駐車の合図

駐車場で車を停めようとする際に、ハザードを点けるドライバーをよく見かけます。
これは「ここに停めます」という意思を周囲に示す合図として広まった使い方ですが、法律で決められたルールではありません。
もともとハザードは緊急時に使うものなので、駐車のために点ける必要はないのです。
ただし混雑した駐車場や空きが少ない状況では、周囲に意図を伝えることで無用なトラブルを防げることもあります。
あくまで慣習的なサインであり必須ではありませんが、混雑した駐車場では「これから停めます」という意図を示すことで、周囲との接触やトラブルを防ぐ助けになる場合があります。
【使用例⑥】バック時のリバースハザード

駐車場では「駐車のサイン」としてハザードを点ける人がいる一方で、バックする瞬間にハザードを点灯する人もいます。
これが通称「リバースハザード」と呼ばれる使い方です。
法律で決められたルールではなく、教習所でも正式には教えられませんが、周囲に「これから後退します」と知らせる合図として一定の効果があります。
歩行者や他の車に対して注意を促す点では便利ですが、あくまで補助的なサイン。
基本は後方確認と徐行が前提であり、ハザード点灯だけに頼るのは危険です。
慣習的に広まった方法の一つとして覚えておくとよいでしょう。
【使用例⑦】濃霧など悪天候での点灯

濃霧で前方の視界が極端に悪いとき、後続車に存在を知らせるため一時的にハザードランプを点ける例があります。
JAFも「徐行時の合図として一時使用は有効」としていますが、常時点灯は誤解を招くため避けましょう。
基本はロービーム点灯が推奨され、フォグランプがあれば併用が効果的です。
フォグは霧を透過しやすく、路面を照らして視認性を高めます。
一方、スモールランプのみでは車の存在が見えにくく危険です。
濃霧時は「見える」だけでなく「見られる」意識を持ち、状況に応じてランプを正しく使い分けることが大切です。
【使用例⑧】救急車接近時の対応

救急車がサイレンを鳴らして接近してきた場合、一般車両は進路を譲る義務があります。
ではこの時、ハザードランプを点けるべきか迷う人もいるかもしれません。
実は、進路変更や停止の意思表示としてウインカーやブレーキランプで十分とされており、ハザードは基本的に不要です。
むしろ意味があいまいなハザードは、周囲のドライバーに混乱を与える可能性があります。
道路状況やタイミングによっては一時停止することもあるでしょうが、その際も通常通りウインカーやブレーキ操作で丁寧に対応しましょう。
大切なのは「緊急車両の通行を妨げないこと」と「周囲に誤解を与えない行動」です。
【使用例⑨】工事車両の点けっぱなし

工事現場や作業中のトラックが、長時間ハザードを点けっぱなしにしているのを見たことはありませんか。
これは「作業中である」ことや「周囲に注意してほしい」という合図で、業務車両では慣習的に使われています。
一般車両に対して法的に認められた特例ではありませんが、作業上どうしても停止時間が長くなるため、ハザードで注意を促しているのです。
ただし一般のドライバーが同じように長時間点灯すると、「故障か?」「なぜ停まっている?」と誤解を招くこともあるため避けましょう。
【使用例⑩】海外とのギャップ

日本で広く行われている「サンキューハザード」は、韓国でも似た使い方が見られますが、アメリカやヨーロッパでは逆にNG行為とされることが多いです。
理由は「走行中のハザード点灯=緊急事態」と捉えられるからです。
また、日本では駐車場で停める際にハザードを点ける光景がよく見られますが、アメリカでは“故障車”と誤解される可能性が高く、場所取りサインとしては通用しません。
一方、日本だとまだ浸透していない「渋滞末尾でのハザード」は、ドイツではアウトバーンで義務に近い重要なマナー。点けないと逆に危険だとされます。
このように「日本では普通でも、海外ではNG」またはその逆が多く、ハザード一つで文化の違いがはっきり表れるのです。
まとめ|安全な使い方を知って、正しい合図にしよう
ハザードランプは本来「緊急時の合図」として装備されていますが、日本ではサンキューや駐車中の合図など、慣習的に広まった使い方も多く見られます。
どれも違法とまでは言えませんが、あくまで補助的な意思表示であることを忘れてはいけません。
大切なのは「自分のため」ではなく「周囲に正しく伝えるため」に点灯すること。
走行中の常時使用や誤解を招くような点け方は避け、状況に応じて臨機応変に使う姿勢が求められます。
国や地域によって解釈が違うこともあり、ハザードは交通文化の一部とも言えます。正しい知識を持ち、安全な合図として活用していきましょう。