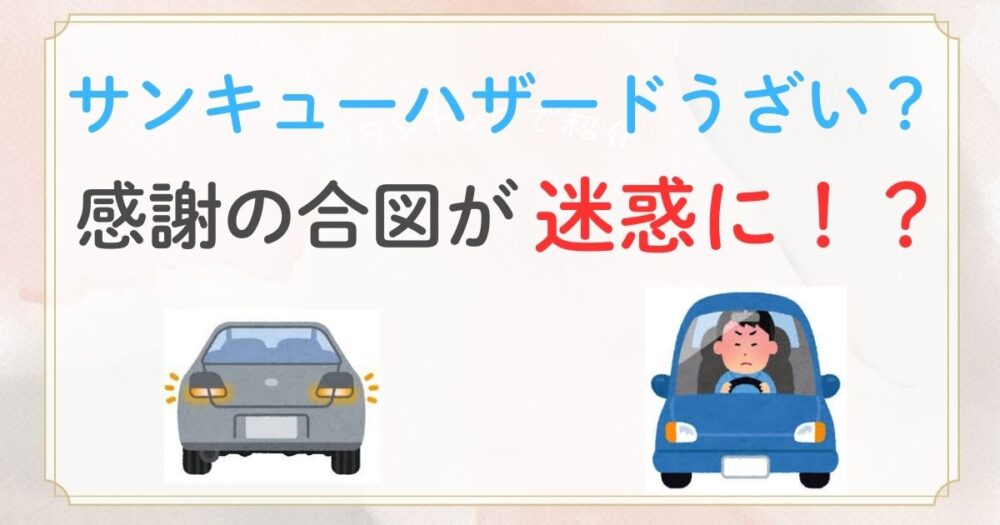サンキューハザードは、日本独自のマナーとして広く浸透しています。
ただ近年は、「しないと不愛想に見られる」といった空気が強まり、感謝のマナーがいつの間にか当然の行為として求められるようになっています。
実際には、サンキューハザードを行わない地域もあり、「うざい」「まぶしい」といった否定的な声も少なくありません。
さらに、海外では同様のマナーが通じない、あるいは走行中のハザード使用が禁止されている国もあることから、サンキューハザードは日本特有の文化とされ、「マナー疲れ」の象徴として語られることもあります。
本記事では、サンキューハザードをめぐる賛否や地域差、その背景にある感情までを丁寧に掘り下げて解説していきます。

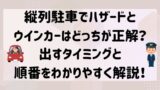
そもそもサンキューハザードとは?
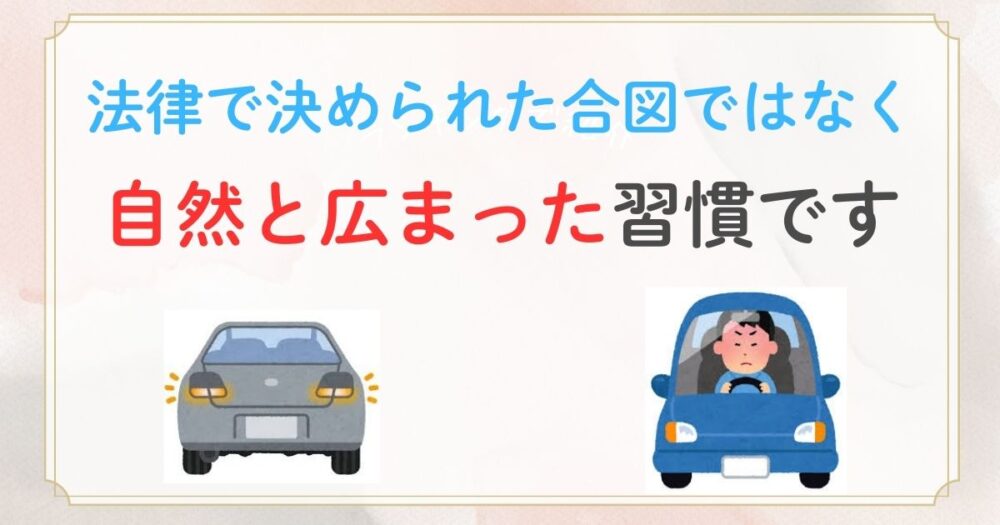
サンキューハザードとは、進路を譲ってもらった際などに感謝の気持ちを示すため、ハザードランプを一瞬点灯させる習慣のことです。
もともとは長距離トラックドライバーの間で広まった合図とされ、今では一般のドライバーにも広く浸透しています。
とはいえ、ハザードは本来「非常点滅表示灯」として、故障時や緊急停車時に使うことを目的とした装置です。
法律上は「お礼」用途として明確に定められているわけではなく、あくまでマナーの一つとして行われているにすぎません。
そのため、状況によっては誤解やトラブルの元になるケースもあり、見直す声も一部で出始めています。
なぜ「うざい」と思う人がいるのか
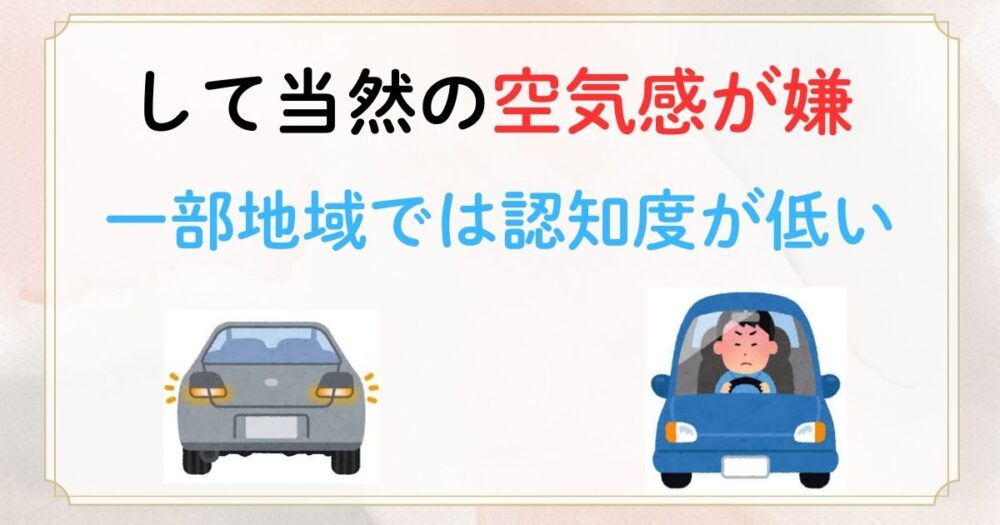
しない地域もあるサンキューハザード、常識のズレからうざいと感じる?
サンキューハザードは全国的に広まっているように思われがちですが、実際にはしない地域も存在し、浸透度には大きな差があります。
JAFの調査によれば、関東や中部では多くのドライバーが当たり前のように使っている一方、東北や沖縄などでは認知度が低い傾向にあるとされています。
そのため、突然のハザードに驚かれたり、意味が伝わらず戸惑われたりするケースもあるようです。
「みんなやっている」という感覚が、実は一部地域では通じにくいこともある…
そんなギャップが、うざいと感じられる背景のひとつになっているのかもしれません。
サンキューハザードが当たり前?その空気感が逆にうざい?
サンキューハザードは本来、必ず行うべきものではありません。
道路交通法にも明記されたルールではなく、あくまで任意のマナーです。
しかし近年では、
「譲ってもらったらハザードを点けるのが常識」
「しないと不愛想で不親切に思われる」
といった空気感があります。
中には、ハザードを点けなかったことで「譲ってやったのに礼もないのか」と、パッシングしてくるドライバーもいるほどです。
マナーがいつの間にか義務として扱われ、それを当然と求める空気が生まれると、気持ちを伝える行為も、逆に重荷や違和感として受け取られるようになります。
実際に、そうした空気を「うざい」と感じる人も一定数いて、マナーの押しつけに対する疑問やジレンマが背景にあります。
海外では通じない?
日本ではサンキューハザードが定着しつつありますが、海外では同様の合図が通じない、あるいは状況によっては誤解されることもあります。
特にヨーロッパの一部では、「感謝はジェスチャーで伝えるもの」という考えが一般的で、いきなりの点滅に「どういう意味?」と戸惑われることもあります。
実際、ドイツでサンキューハザードを使った日本人ドライバーは「相手に怪訝そうな反応をされ、日本との違いを実感した」というエピソードもあります。
こうした文化の違いが、時に思いやりとしてではなく、意図が伝わらない行動として受け取られてしまうこともあるのです。
実は危険?サンキューハザードのデメリット
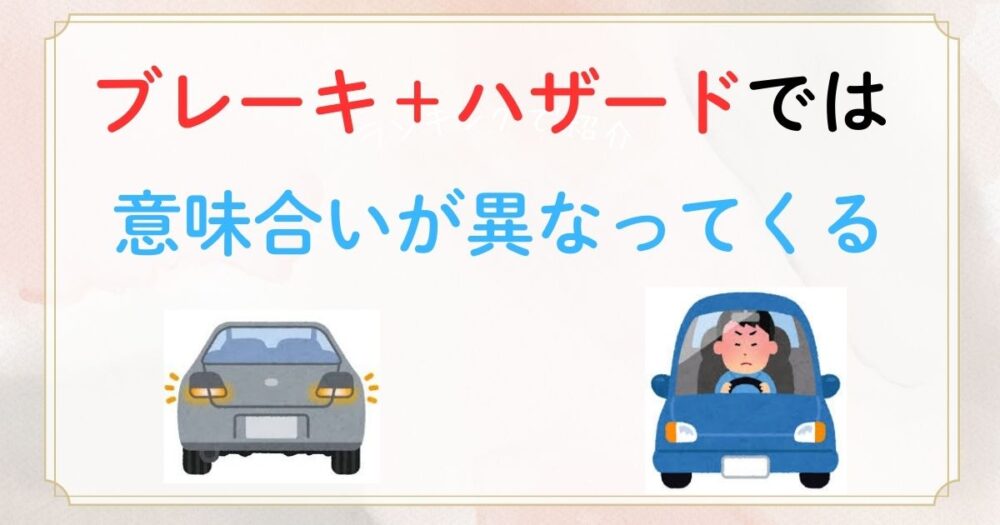
誤解による事故リスク
感謝のつもりで点灯したハザードが、かえって危険を招く場面もあります。
たとえば、走行中に突然ハザードを点けられると、後続車は「停車するのか?」と勘違いしてブレーキを踏む可能性があります。
特に高速道路や渋滞中では、追突のリスクが高まります。
また、信号も交差点もない場所で不意にブレーキを踏まれ、その後にハザードが点くと、意味が伝わらず混乱を招くケースもあります。
本来の使い方から外れているからこそ、合図の意図が誤って伝わる危険性があるのです。
安全運転義務違反となる可能性
サンキューハザードは法律で禁止されているわけではありませんが、状況によっては「安全運転義務違反」とみなされる可能性があります。
本来、ハザードランプは故障や事故、停車時など、緊急を知らせる目的で使用される装置です。
違反として処理されるケースは稀とはいえ、サンキューハザードのつもりで点灯したことで万一事故が発生すれば、
「不要かつ不適切な使用」として法的責任を問われる可能性は否定できません。
「サンキュー」を伝える別の方法もある
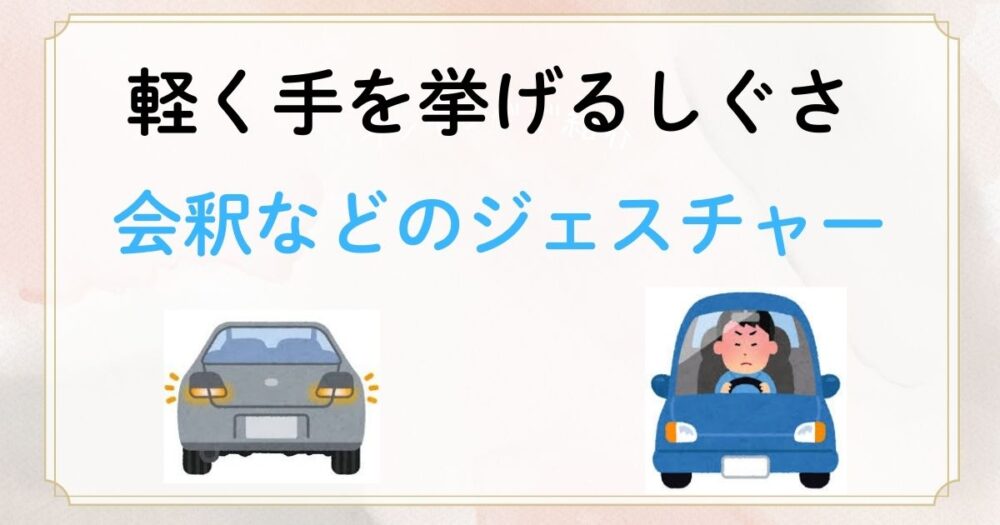
サンキューハザードに頼らなくても、感謝の気持ちを伝える手段は他にもあります。
たとえば、軽く手を挙げるしぐさや、後方を振り向いての会釈は、表情や雰囲気が伝わりやすく、誤解を生みにくい方法です。
昼間であればジェスチャーのほうが伝わりやすい場面もあり、運転に慣れたドライバーほど自然に行っている印象もあります。
ハザードに頼らずとも、心のこもった小さな動作が、より確かな感謝として相手に伝わることもあるのです。
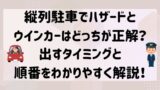
まとめ|共感がズレを生み、マナーが圧力になることもある
サンキューハザードは、元々は「ありがとう」を伝える温かなマナーでした。
しかしその気持ちが、いつの間にか「するのが当然」という空気に変わると、気遣いのつもりが逆に圧力になってしまうこともあります。
地域によっては「そもそもやらない」文化もありますし、「まぶしい」「うざい」と感じる人もいます。
また、海外では受け入れられない国や通じない場面もあることを考えると、必ずしも“正解”とは限らないのです。
大切なのは、自分の感覚を押しつけるのではなく、相手を思いやる姿勢。
マナーが気持ちよく届くには、強制や期待ではなく、自然な気持ちのやり取りが基本です。