走行距離課税は「走った分だけ負担する」という一見公平に見える制度です。
しかし、実際には地域や生活環境によって影響は大きく異なり、単純に導入すれば公平性を損なう恐れがあります。
現在、日本ではガソリン税の暫定税率の廃止議論と並行して、代替税として走行距離課税の検討が進んでいます。
すでに世界各国では同様の制度が試行され、成功例もあれば大きな反発を招いた失敗例も存在します。
公平な制度設計の成否は、まさにこれらの経験に学べるかどうかにかかっています。
本記事では、世界の成功例と失敗例を比較しながら、日本で走行距離課税を導入する際に必要な条件を徹底解説します。


走行距離課税とは何か?
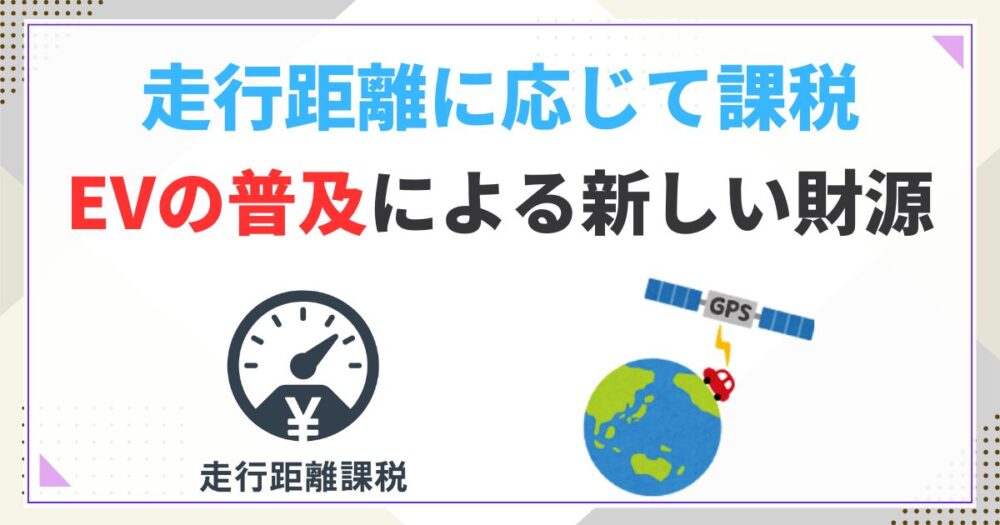
走行距離課税とは、その名の通り車の走行距離に応じて課税額が決まる仕組みです。
従来のガソリン税は燃料消費量に比例しましたが、EVの普及で税収が減る中、新しい財源として注目されています。
ただし「走った人が多く払う」という単純な発想だけでは公平性を保証できません。
地域の交通事情、所得水準、車の用途など複数の要素が絡み合うため、制度設計次第で公平にも不公平にもなるのが実情です。
世界の成功例から学ぶ
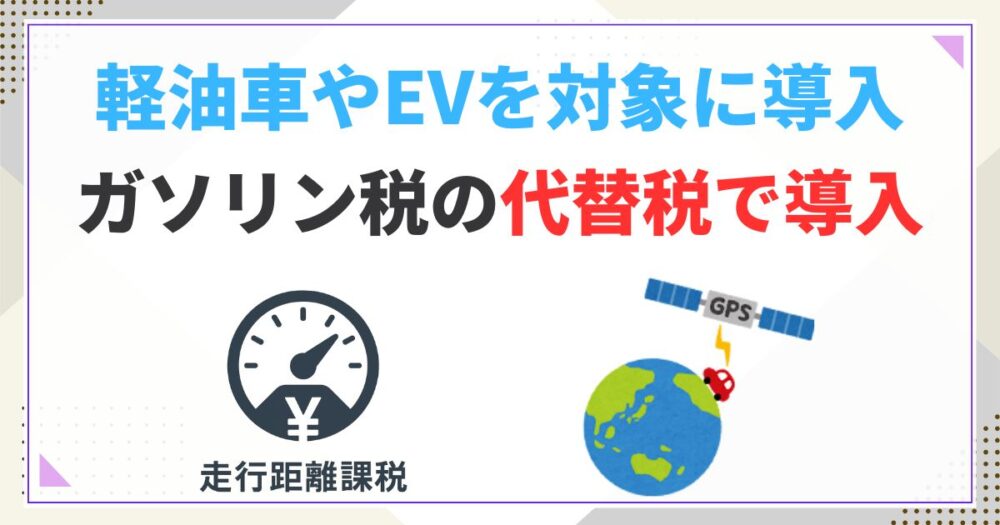
走行距離課税は「失敗例」が取り上げられがちですが、実は成功した国や地域も存在します。
うまく機能している制度には、共通して利用者の理解を得る工夫や透明性の高い仕組みが整えられている点があります。
ここではニュージーランド、ドイツ、アメリカ・オレゴン州の事例を見ながら、成功の要因を探っていきます。
ニュージーランドのRUC制度
ニュージーランドでは「RUC(Road User Charges)」として、軽油車やEVを対象に走行距離課税を導入しています。
料金は事前に購入する距離単位のチケット制で、透明性が高く脱税も防止しやすいのが特徴です。
導入後は税収が安定し、道路整備への還元も明確化されました。
制度が定着した背景には、シンプルで分かりやすい仕組みと国民への丁寧な周知があったといえます。
ドイツの大型車課税制度
ドイツでは高速道路を走行する大型トラックに「重量」「排出ガス量」「走行距離」を基準に課税しています。
専用の車載器で距離を計測し、料金は道路インフラ整備に直接充てられています。
これにより物流業界の環境負荷低減が促されただけでなく、道路維持費を利用者が公平に負担するという原則も浸透しました。
高度な技術を使った計測と透明な使途が成功の要因です。
アメリカ・オレゴン州の実証実験
アメリカ・オレゴン州では、ガソリン税に代わる形で走行距離課税の実証実験が行われました。
GPSや車載機器を利用して距離を記録し、複数の計測方式から利用者が選べる柔軟な仕組みを導入。
位置情報を提出しない方法も選べる設計により、個人情報保護に配慮した運用が評価されています。
強制ではなく選択制を取り入れた点が、住民の理解を得る大きなポイントとなりました。
失敗例からの教訓
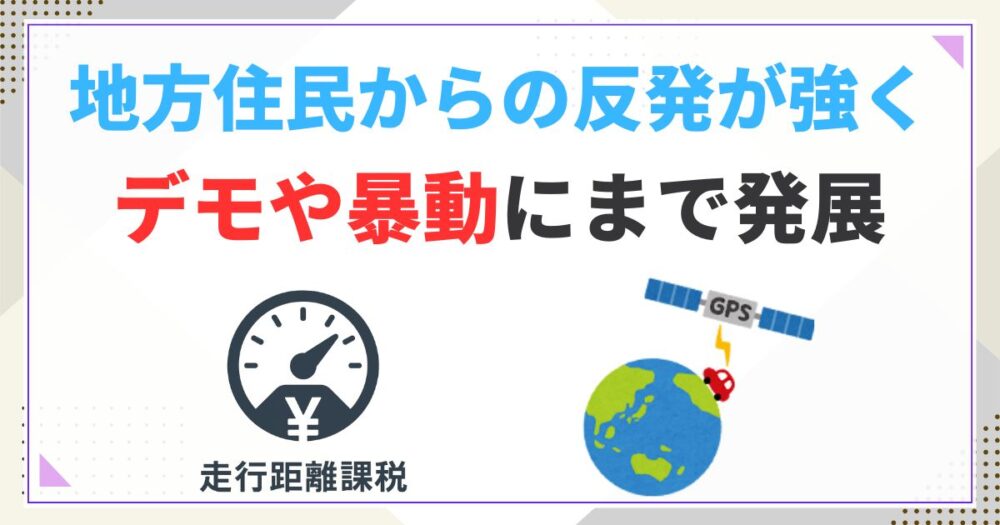
走行距離課税は理論上は公平な仕組みですが、導入がうまくいかずに撤回や見送りとなった事例も少なくありません。
共通するのは「利用者の納得感を得られなかったこと」と「制度設計の甘さ」です。
課税の使途や負担感に疑問が生じると、強い反発を招き制度自体が立ち行かなくなります。
フランスのエコタックス
フランスでは、トラックに対して環境目的の課税「エコタックス」を導入しようとしました。
しかし物流業界や地方住民からの反発が強く、道路封鎖デモや暴動にまで発展し、結果的に制度は撤回されました。
失敗の背景には、負担が一部業界や地域に集中しすぎたこと、合意形成を十分に行わなかったことが挙げられます。
その他の失敗/見送り事例
欧州や一部の州レベルでも、走行距離課税は検討されたものの頓挫したケースがあります。
プライバシーの侵害につながるGPS追跡への懸念、徴収コストがかかりすぎる問題、低所得層への負担増などが理由です。
制度の目的は理解されても、運用面で信頼を得られなければ長期的には成立しないことを示しています。
日本における導入への課題
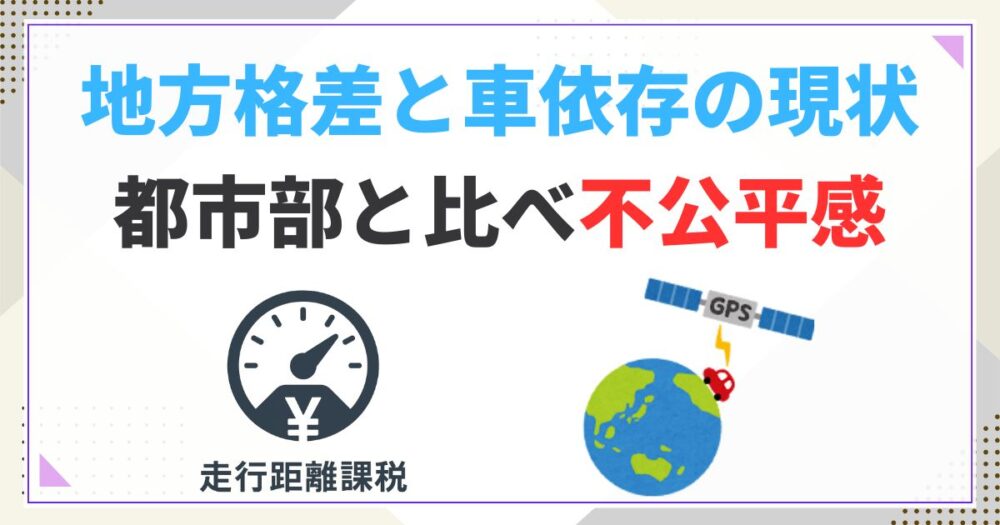
日本ではガソリン税収の減少とEV普及の進展により、新たな税制の検討が避けられない状況です。
走行距離課税はその候補として注目されていますが、日本特有の事情を考慮しないと制度は不公平さを助長しかねません。
ここでは日本が直面する課題と導入の可能性を整理します。
地方格差と車依存の現状
地方では公共交通が十分に整備されておらず、車は生活必需品です。
都市部と同じ基準で課税すれば、通勤や買い物のために長距離を走らざるを得ない人ほど負担が増え、不公平感が強まります。
特に高齢者や子育て世帯にとっては生活の質を直撃する問題です。
EV普及・燃料税収減と移行期問題
ガソリン税の減収は財政に直結するため、EVやハイブリッド車にも適用可能な新制度が求められています。
ただし、既存のガソリン税を即廃止して走行課税に一本化すると混乱が生じやすく、一定期間は併用が現実的です。
過渡期の制度設計こそ、国民の理解を得るポイントになります。
技術・監視・プライバシー課題
走行距離を正確に把握するには、車載器やGPSを用いたデータ収集が不可欠です。
しかし「監視されている」という懸念や不正防止のコストが問題になります。
制度を円滑に運用するには、データ利用の透明性やプライバシー保護を徹底し、利用者が安心できる環境を整えることが重要です。
公平な制度にするために
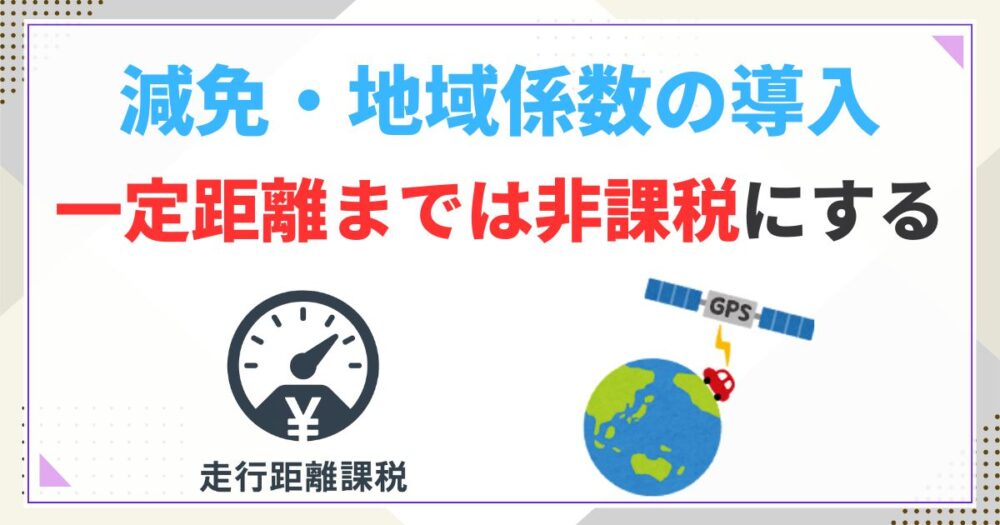
世界の成功例と失敗例から明らかになったのは、走行距離課税が公平に機能するかどうかは設計次第だということです。
単純に距離だけで課税すると不満が噴出しますが、利用実態に応じた柔軟な調整を組み込むことで納得感を得られます。
ここでは公平性を保つための条件を整理します。
減免・免税枠・地域係数の導入
一定距離までは非課税にする「免税枠」や、公共交通が乏しい地域に適用される「地域係数」を導入すれば、不公平感を和らげられます。
基礎的な生活に必要な走行分は保護し、それ以上の利用に応じて負担を増やす方式が現実的です。
所得・用途別の調整(商用車・業務用途配慮)
物流業や営業車など業務用途の走行は、生活や経済活動に不可欠です。
単純課税ではコストが物価に転嫁され、消費者全体に不利益をもたらします。
商用車には控除を設けたり、所得水準に応じた緩和措置を導入するなど、利用目的に即した調整が必要です。
合意形成と透明性/段階的導入の重要性
制度を急に導入すると反発が強まり失敗につながります。
まずは一部地域や対象車種に限って試行し、実データを踏まえて修正を重ねる段階的導入が効果的です。
さらに、徴収した税金の使い道を明確にし、道路整備や環境施策に活用する姿勢を示すことで、利用者の納得を得やすくなります。
まとめ:制度の公平性は設計次第
走行距離課税は「走った分だけ負担する」というシンプルな仕組みですが、設計を誤れば地域や所得の不公平感を強めてしまいます。
世界の成功例では免税枠や地域係数の導入、段階的な試行など、利用者が納得できる工夫がありました。
一方で失敗例は、合意形成不足や負担の偏りが原因で強い反発を招いています。
日本で導入を検討するなら、地方や業務用途への配慮、プライバシー保護を重視することが欠かせません。
制度は「設計次第で公平にも不公平にもなる」という前提を踏まえ、慎重な合意形成が必要です。


