走行距離課税の導入が議論され始めています。
ガソリン税に代わる新しい財源とされていますが、地方に暮らす人々からは「不公平だ」という声が強く上がっています。
都会では電車やバスを使えば車なしでも生活できますが、地方では通勤や買い物、子どもの送迎まで車が欠かせません。
走行距離が長くなるのは避けられず、課税が生活を直撃する可能性があります。
本記事では、この制度がなぜ地方にとって不公平とされるのか、その背景や影響を整理して解説していきます。


走行距離課税とは?導入の背景と仕組み
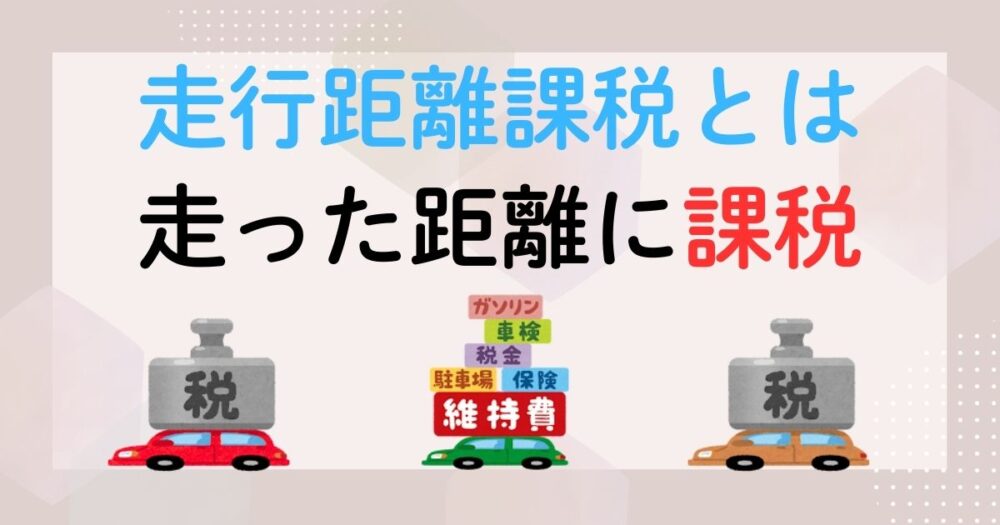
走行距離課税とは、その名の通り「走った距離に応じて税金を課す」制度のことです。
現在の道路財源は主にガソリン税ですが、EVやハイブリッド車の普及によって燃料消費量が減り、税収が減少してきました。
そこで新たな財源として検討されているのが走行距離課税です。
実際にどのように距離を計測し、徴収するかは議論の段階ですが、国としては「公平に負担を分け合う仕組み」として導入を模索しています。
地方にとって不公平といわれる理由
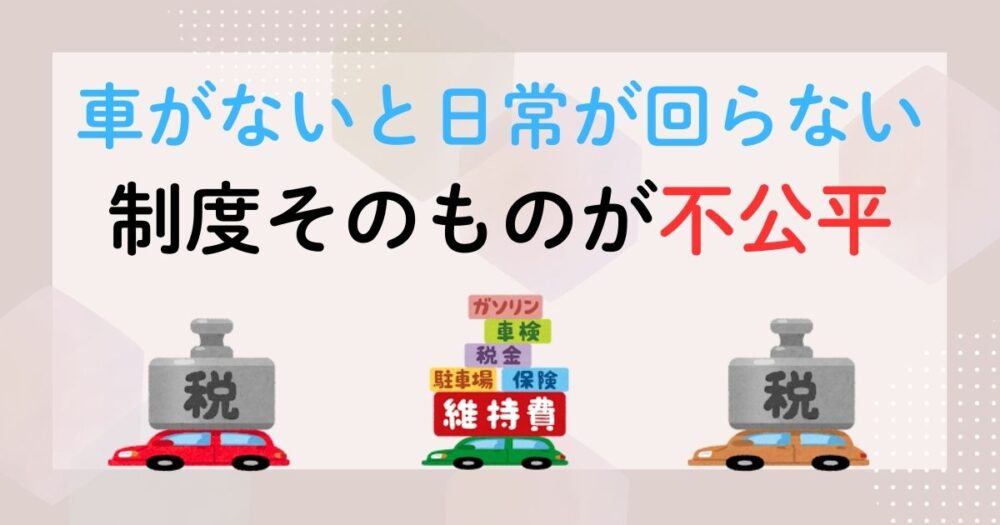
公共交通の少なさが生活を直撃
地方では「車がないと日常が回らない」現実があります。
具体的な車依存の場面を整理すると、課税が生活直撃になる理由が見えてきます。
- 通勤・通学で毎日数十kmの移動
- スーパー・病院・役所が遠く、日常の用足しも車前提
- 保育園や部活の送迎、介護・通院の付き添いも車頼み
- 電車・バスは本数が少なく代替が利かない
こうした日常生活に欠かせない移動にまで課税されれば、地方では都会以上に負担が重くなり、不公平だと感じる大きな要因となります。
既存の自動車税との多重負担感
もともと自動車には複数の税が重なっています。名称と役割を押さえると、重ね掛けへの不満が伝わりやすくなります。
- 自動車税(種別割)=毎年の保有に課税
- 自動車重量税=車検時に重量に応じ課税
- 環境性能割(旧・取得税の後継)=購入時に性能で課税
- 燃料関連税(揮発油税・地方揮発油税 等)+消費税
ここへ走行距離課税が加われば、ただでさえ多重課税と言われる状況にさらに負担が増し、地方では「制度そのものが不公平だ」と受け止められる可能性が高まります。
物流・生活コストにも影響
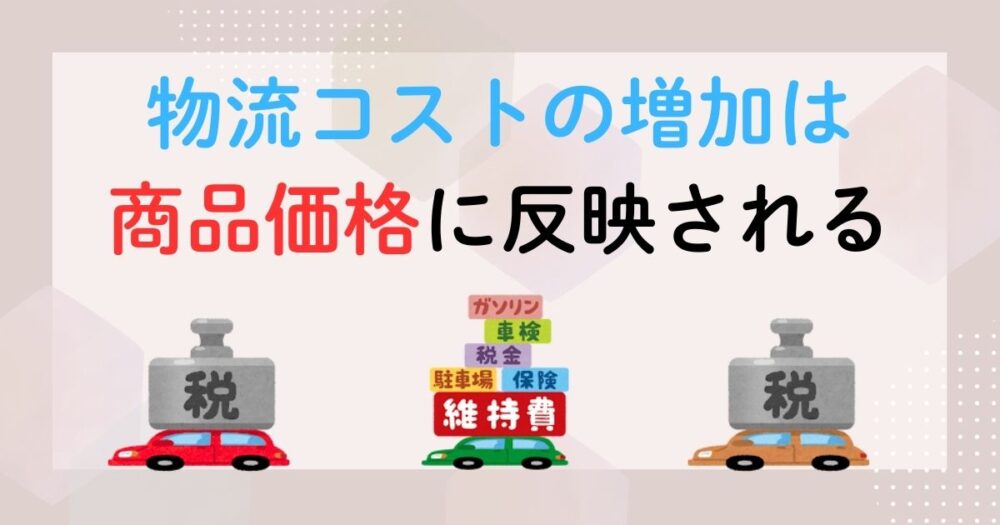
物流業界への打撃
走行距離課税は、長距離輸送を担う物流業界に重くのしかかります。
特に地方では中継拠点が少なく、1台あたりの走行距離が長くなりがちです。
その分、課税額も高くなり、すでに燃料費や人件費が圧迫する中でさらに負担が増す構図です。
- 走行距離が長く、課税額が高くなりやすい
- 既存のコストに課税が上乗せされる
- 中小業者ほど影響が深刻
- 地域物流網の維持が難しくなる
こうした影響は、やがて地方の物資供給体制そのものを弱らせる恐れがあります。
家計への物価転嫁
物流コストの増加は、最終的に商品価格に反映されます。
食品、日用品、燃料など、生活必需品の多くはトラック輸送に依存しており、課税による負担は消費者が背負う形となります。
地方は都市部よりも物資の輸送距離が長いため、価格上昇の影響を受けやすいのが実情です。
結果として、ただでさえ生活コストが高くなりがちな地方住民の家計に、さらなる圧迫が加わる可能性が高いのです。
公平性をどう担保するか?
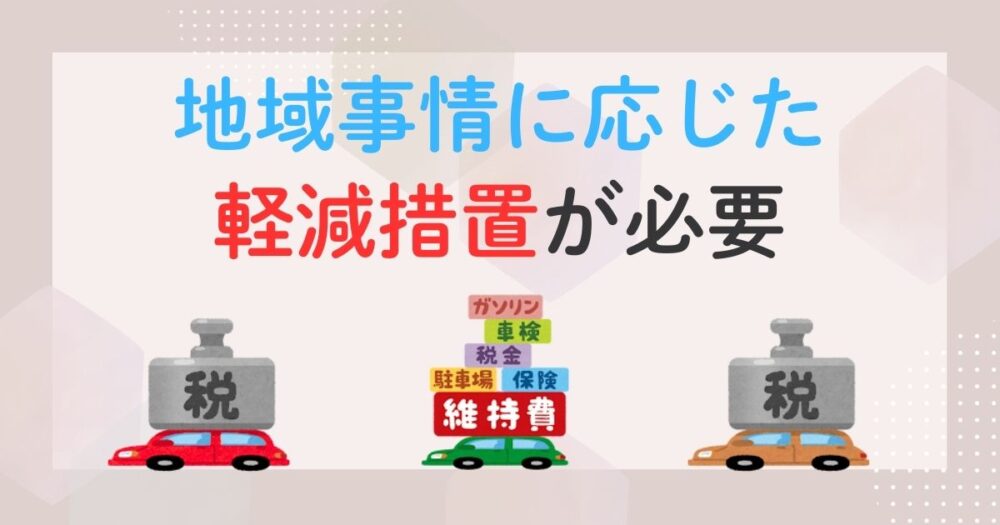
地域格差を考慮した軽減措置
「全国一律」で課税すれば、生活に車が欠かせない地方が明らかに不利になります。
制度設計の段階で次のような緩和が検討に値します。
- 地域係数の導入(公共交通の充実度や車依存度を反映)
- 生活必需距離の非課税枠(通勤・通院・送迎などの移動に一定距離の免税枠を設ける)
- 物流・タクシーなどの業務走行への控除や上限設定(職業上やむを得ない走行に対する負担軽減)
- 公共交通が事実上使えない地域への課税軽減措置(鉄道や路線バスがない地域など、代替交通手段がない地域に特例を設ける)
こうした制度的配慮があって初めて、車が必須な地域の“避けられない距離”に対する公平性が具体化します。
既存税制との調整が不可欠
走行距離課税を導入するなら、既存の自動車関連税との整理が欠かせません。
重量税や環境性能割など、保有や購入時にすでに課されている税に加えて、新たに使用距離に応じた課税が加われば、制度全体として過重な印象を与えるのは避けられません。
課税体系を見直し、「どの税を減らし、どこを距離課税で補うのか」を明確にすることが、公平性の確保には不可欠です。
制度の全体像が不明確なまま導入されれば、納税者の不信感が広がるだけでしょう。
世界の走行距離課税制度と日本の課題
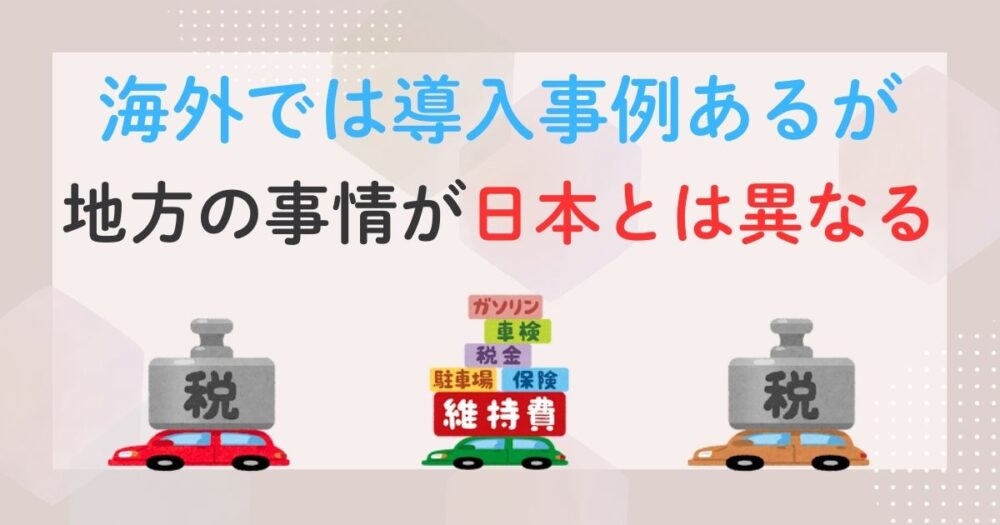
走行距離課税は日本だけの議論ではなく、海外ではすでに導入事例があります。
アメリカの一部州では、EVの普及に伴い燃料税に代わる財源として走行距離課税を採用しています。
ただし、アメリカは都市間移動が前提であり、日本の地方事情とは異なります。
日本の場合、過疎地や高齢化が進む地域では車が生活そのものを支えるため、同じ制度をそのまま当てはめると不公平感が拡大しかねません。
日本独自の課題に即した制度設計が求められます。
家計への影響を試算してみる

例えば、1km=1円で課税された場合の試算は次のとおりです。
- 年間1万km走行(都市部の平均的利用) → 年間1万円の負担
- 年間2万km走行(地方の一般的通勤+生活利用) → 年間2万円の負担
- 車2台持ち世帯(地方に多いケース) → 年間4万円以上の負担
このように、地方では走行距離と台数の両面で負担が膨らみやすく、家計への影響は都市部より大きくなります。
まとめ:地方に寄り添った制度設計が不可欠
走行距離課税は、ガソリン税に代わる新たな財源として期待されていますが、そのまま導入すれば地方住民に過度な負担を強いることになります。
車が生活の足である地域に一律で課税するのは不公平感を招き、社会的な分断につながりかねません。
制度を進めるのであれば、地域差を考慮した特例や既存税制の見直しなど、地方の実情に寄り添った設計が不可欠です。
公平性を欠いた課税は、国民の納得を得られないでしょう。


